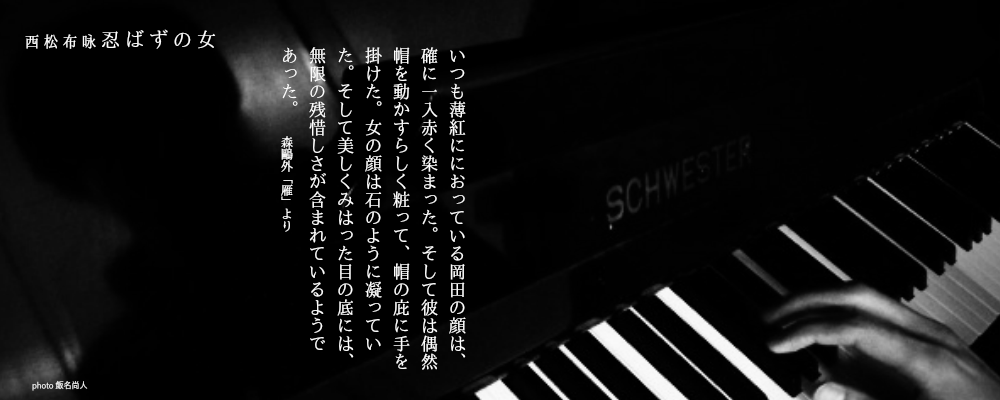運命、タイムトリップ、そして自由。
2013.6.18
文:水野立子
写真:GO (photographer) 飯名尚人
その日私は、西松布咏さんの妖艶な江戸唄に聞き惚れながらしばし浮世放れした気分で、客席のシートにピンッと背筋を伸ばして座っていた。4曲ほど演奏が終わり、いい塩梅で粋な空気が肌に浸透してきた頃だろうか。「えっ?」と思わず声が出そうになった。鷗外の小説「雁」のあらすじを布咏さんが語った時だ。東大生の岡田が、上野の不忍池にいる雁を逃がしてやろうと投げた石が、自分の意思に反し逆に射止めてしまった、というくだり。これはまさに、今まで誰にも云うことができなかったけれど、私の子供のころの実体験と同じ話だったのだ。心の奥に閉じ込めていた記憶、いわばトラウマ。そのあたりから、私はもう背筋を伸ばして座っていることができなくなり、シートに深く身を沈め、次々と想起してくる自分の記憶と、舞台で起こっている出来事を行きつ戻りつし始めた。何が本当に起きたことで、何がつくりものの世界なのか。この日の「忍ばずの女」という舞台作品に、私はたっぷりと翻弄されることになった。

写真:GO
そうなのだ、岡田が雁の首に命中させて殺してしまった石を握るその手の感触が、まるで自分の手の中にある石のように感じられる。
あれは小学校5-6年の頃、家族で河原にドライブに行った時のこと。車を背丈ほどある葦の群生の脇に止め、外の空気を吸いに休憩することになった。数メートル先にあるその葦の藪の中に、まず父親が石を投げ入れた。家族もそれに続いた。子供には届くか届かないかほどの遠すぎる距離のそこをめがけて、力一杯に投げる石投げゲームのつもりだったのだが、何回目かの私の投げたその一投石が藪の中に入った瞬間、ぐっ、という何とも鈍い音がして数羽の鳥が飛び立った。その時父が、「もしや、今のお前の投げた石で鳥が死んだかもしれないよ。」と言ったのだ。その声色を今でもはっきり思い出せる。自分が本当に鳥を殺してしまったのか、そうでなかったのか。確かめる勇気はなく、その藪の方に向かって歩き出すことが、とうとうできずじまいだった。ほかの家族もそれを見に行こうとは言い出さず、もしかしたら、瀕死の鳥を皆で見捨てたのかもしれないのだ。そんなどうにも救いがたい思い出話。思い返してみれば、その頃の似たような悪意無き悪行の記憶が次々と蘇ってきた。蟻の巣に続く蟻道を指でほじり、大量の蟻が右往左往して出てくる穴の指先に残る、粒状の土の手触りの良さ。必死になって虫取網を振り回していたら、ひっかかった蝶が粉々になってしまい、後に残った鱗粉の美しくもざらついた輝き。小さな罪なき生命を摘んでしまった罪悪感とリアルな感触。岡田も、やはり、随分あとになってから、こんな苦い思いを噛みしめたのだろうか。

写真:GO
演出家の飯名さんは、「雁」のテーマは“運命”だと解す。空に広がる木々の葉が、ゆっくりとどこまでも続くように流れる映像シーンがあった。モノトーンのように写されていたはずの葉の色が、辻隼人さんのピアノの旋律と重なり、私には光を一杯に浴びた鮮やかな緑色に変わり迫ってくるよう。此処其処にばら撒かれた運命を引き受けるための“覚悟”を促されているような、そんな感覚に陥った。だからなのか、まるで思い出したこともない傷のような記憶が呼び覚まされたのかもしれない。飯名さんの映像は、いつだって想像させる隙間がある。
一方で、“運命”を軸に展開していく物語と対比するように、運命を受け入れつつも、それに抗うように生きたいと願うお玉と、布咏さんのつくりあげる「忍ばずの女」に込められた魂が重なってみえてくる。“忍ぶ女“から“忍ばず・忍ばない女“への強烈な意思転換を試みるお玉の決心、その女心の行き場のなさと未来に託す希望―不安定だけれど凛とした思いが、江戸唄を唄い続け、今の世にも残していきたいという布咏さんの生涯をかける芸と合わさり、一層の強さで舞台の上から迫ってくる。「忍ぶ」思いとは、とてつもなく重く深い。「心に刃と書いて忍ぶ。わかるような気がします。」と布咏さんが語っていた。私は果たして、「忍ぶ」ほどの思いをどれほど抱えて生きているだろう。
第一部の〆の曲、布咏さんと辻さんのコラボ演奏曲「明けの鐘」は、お玉と岡田になった二人が、お互いの奏でる音楽に不協しつつ共存していた。異次元の世界から聞こえてくるピアノと、私には歌詞を聞き取れず唄の意味はわからなかったが、唸るような、泣いているような、ただただ切ない思いが、唄というよりボイスといったほうがいいのだろうか、幽玄世界へと誘われていった。舞台の真ん中に座って唄っている布咏さんの身体から、お玉の分身がひゅるひゅると抜けだし、無縁坂を颯爽と歩く岡田の周りをまとわりつくように浮遊している風景がよぎった。
写真:飯名尚人
「雁」の物語の要のエピソードに蛇と紅雀の一件がでてくる。「忍ばずの女」では、大野慶人さんの踊りと、飯名尚人さんの映像の2つのコントラストが面白かった。飯名さんは、印象的な短編映画のようなつくりで、まるで登場人物の人生の逸話を思わせるように、うまい具合に舞台作品に映画を挿入していく。慶人さんの蛇の手がいやらしく鳥籠に侵入、鳥を襲う手のダンス。鳥籠を前にお玉が茫然と座り込み、寂しげな気持を写すようにピントがぼやけて見えない。この暗示的な男と女の運命の出来事と、チュンチュンという映画の中の雀のさえずりに誘われて、私にまた別の記憶が蘇ってきた。
そう、あれはやはり小学生の頃、鳥好きな家だったようで映画の中と同じような鳥籠がいくつもあった。思い出せるだけでも、ウグイス、メジロ、アオジ、モズ、ホオジロ、カナリヤ、インコ、手乗り文鳥、キンカチョウ。そして緑や赤のカラースプレーを塗られ、店先で売られていた紅雀。そのうち、鳥籠だけでは飽きたらず、庭の一画に金網で囲われた大きな鳥小屋をつくることになった。ところが、その金網をかいくぐり、蛇が鳥を狙い出没するという事件が起きた。これも小説「雁」と同じ。あいにく家には、岡田のような勇敢な好青年はいなかったようで、小屋を壊して鳥を放すことになった。ルビー色に光る愛らしいメジロ3羽を鳥籠に入れて、山に持って行き放したことを覚えている。鳥籠の扉をあけ「さあ、自由になれ」と声に出してみたものの、この先、自分一人で生きていけるのだろうか、と子供心に不安がよぎった。
もしかしたら、きっと、お玉と岡田の運命の先は、まったく違う生き様が待っていたのかもしれない。「天の神様の言うとおり、あのねのね。」なのか、いやいや、そこを自分の意志で変えてみせるのか。必死で変えた結果だと思っているだけで、本当はそれも運命のうちなのか。まったくもって、自分の勝手な独り相撲なのか。ますますわからなくなってくる。
この日の舞台では、慶人さんは蛇と鳥を踊られた。地と空のダンス。ぬっと突き出された地を這う蛇の腕と、鳥が空に羽ばたく震える指先、確かなステップ。まさにそれは、運命であり、意志であった。だが不思議なことに、両極であるはずのどちらの踊りからも「自由」そのものが見えた。お玉も布咏さんも、そして私も、どうすることもできない運命や、精一杯の意志さえも、こんなふうに“自由”に変えて生きていくことができたなら。いや、生きてみたいと思った。

写真:GO
[筆者略歴]
水野立子(みずのりつこ)
ダンス作品企画・ディレクター・プロデューサー。Groovism,.Co ディレクター。
暗黒舞踊の始まりといわれる「禁色」上演年に生まれる。79年より舞踏グループ東方夜總会(80年より白虎社)に入るため、東京から京都に家出同然で移住。以後、解散する94年まで在籍し舞踏手、制作として活動。96年から1年間、DTW、Movemennt Research などで学びながら、N.Y.に在住。帰国後、ダンス企画制作を行うGroovism Company、JCDN設立準備室を経て、2000年NPO法人Japan Contemporary Dance Networkの設立より、2013年まで参加し、多数のダンス事業を企画実施。近年では、JCDN作品制作&巡回公演「踊りに行くぜ!!」Ⅱセカンド、DANCE×MUSIC×MOVIE!「ASYL」、「日本ーフィンランド国際共同プロジェクト」など手がける。2012年より金粉ショー The NOBEBOの稽古指導に取り組む。