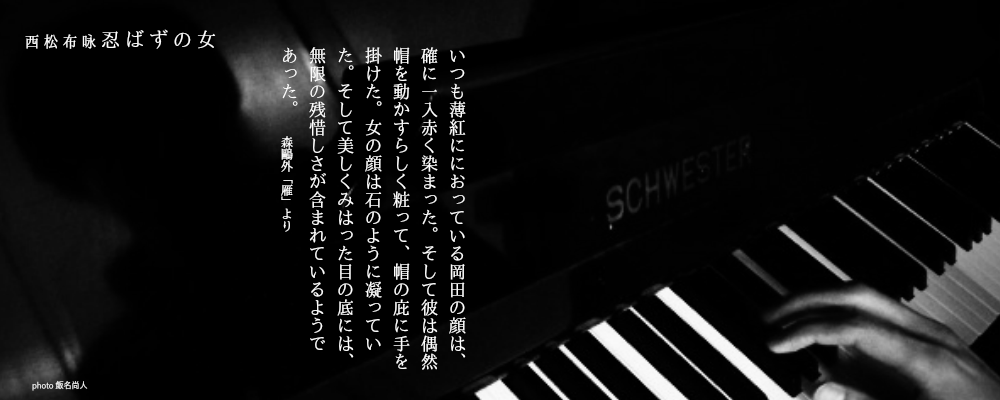"ouroboros"
2013.6.13
文・写真:GO (photographer)

"ouroboros (ウロボロス)"とは「尾を飲み込む蛇」の意。「死と再生」「不老不死」の象徴とされる蛇が、自身の尾を飲み込むことで、回帰、永遠、根源や無限などを意味する。
森鷗外の「雁」という小説がある。ここに書かれたことは、簡単に謂うと、ものの偶然についてではないだろうか。そして偶然とは人の思い込みにも依るところが多く、その偶然が時として他者のそれと繋がり、離れ、運命のように変わっていく。偶然さ故の無情。そして全ては巡り巡ってやってくるのだ。
ジョゼフ・ニセフォール・ニエプスの最初の写真が文政10年。岡田とお玉が無縁坂ですれ違った明治13年には、既にゼラチン乾板の発明により、野外での動く人を撮ることが可能になっていた。もしその二人をカメラを持った「僕」が観ていたらどういう風にシャッターを切っただろうか。

森鷗外の「雁」を原作に、西松布咏さんが「忍ばずの女」を創作したのが1987年。その頃、札幌の高校に通う一学生だった僕は写真どころか舞台というものに触れることも興味も無かったが、同じ北海道出身者として、舞踏家・大野一雄氏のことは知っていた。
それから年月を経て写真家・浅井愼平氏が関わるスタジオのチーフ・アシスタントを務める為に上京した僕が、大野一雄舞踏研究所に通っている舞踏家の方と知り合い、上星川のご自宅の稽古場へと同行したのが2000年の夏。何かのパーティーからの帰りで少しご機嫌だった一雄さんは稽古場に入るなり、もう踊りたくてしょうがないようなご様子だった。
「皆さん、すみません。今日は一雄が踊りたいようなので、少し踊らせてあげてください」
慶人さんがそう言い終わる前に、既に一雄さんは踊り始めていた。慶人さんは稽古場の照明を変え、一雄さんの動きをしっかり見つめながら音楽をかけた。一雄さんの舞踏。それはまるで寄せては返す波のよう。そもそも、いつが始まりで、いつが終わりなのか。手が届く距離なのに届かない。かと思うと離れているのにふと触れられるようにも感じる。時間にして、一時間程、ただひたすら踊り続け、そのまま嬉しそうに、いつもの椅子に踊りながら腰を落として一呼吸。軽い休憩をはさみ、残りの時間は研究生の方々も交え、皆がその空間で踊り始めた。それが初めて舞踏、そして大野一雄さん、慶人さんとの邂逅だった。
全てが終わった時、挨拶もそこそこに
「今度僕に撮らせて頂けませんか?」
と考えるより先に思わず口から言葉が溢れた。
優しく笑う一雄さんと慶人さん。そして「どうぞ。フリースタイルですから。お好きな時にどうぞ。いつでもいらしてご自由に撮って下さい。」
嬉しい反面、目の前で繰り広げられた事を果たしてどうすれば撮れるのか悩みに悩んだ。それから実際にシャッターを切る迄、週3回の研究生の方々の稽古に半年程通うことになった。
手を伸ばした先の闇に舞う桜の花びら。身体の芯へと深く続く宇宙。見えているけれど見えないもの。感じているけれど掴めないもの。それをどう一枚の写真として捉えるか。時の流れを殺すことなく。過去の「想い出」としての一枚ではない踊り続ける瞬間として。
僕が踊る身体を撮りたいと思った原点である。

2010年に他界された一雄さんの3回目の命日にあたる2013年の6月1日。僕が舞台を撮るようになって13年。偶然ついでで森鷗外の「雁」の連載が終わったのが1913年。会場となった高輪区民センターのある白金高輪は、メトロのN03。閑話休題。舞台写真を撮るきっかけとなった一雄さんの命日に慶人さんを撮れるということは僕にとっては内心とても大きなことで、遠足の前の子どもじゃないが妙な緊張だか興奮だかで、前日の夜は、なかなか寝付けなかった。
13年前の一雄さんの写真を手に会場の客席で支度中の慶人さんにご挨拶すると
「あぁ、親父だぁ。今日は命日なんです。はぁ・・・親父だ、親父ですね。今日は宜しくお願いします。」
その言葉で、今日はもう撮れたな、という気分になった。
 初めて生で聴く西松さんの三味線と唄に、花柳千壽文さんの舞。辻隼人さんのピアノと歌、飯名尚人さんの映像。
初めて生で聴く西松さんの三味線と唄に、花柳千壽文さんの舞。辻隼人さんのピアノと歌、飯名尚人さんの映像。
そしてそこで蛇として、雁として、慶人さんが踊る。
今回稽古も見られず撮影に挑んだ僕にとっては初めて観る光景の筈だったが、どこか懐かしく、そして瑞々しく新鮮な時間がそこには満ちていて、それがただただ嬉しく、夢中に、同時にとても冷静に、カメラを構えた。
表現と謂うものは、その瞬間、瞬間を生きていてその現在の生を生ききっているものは常に若々しい命として直そこに在る。ストーリーや演出をふまえて押さえることは勿論大事なことかも知れない。けれど一写真家として対峙するのは、常にその瞬間の生であり命である。永遠を説くつもりは無いが、常に「現在(いま)」を見据えた表現と謂う物はたとえ写真で捉えたとしても決して色褪せない。勿論、その瞬間を逃さず捉えることが出来たらの話ではあるが。
真剣かどうか、そこに想いはあるのか。その場に投げ出された声、腕、脚。内へと振りかざした拳、眼差し、吐息。ファインダーの向こうから届く、聴こえない呼吸に、自分の呼吸を合わせながらシャッターを切る、切る、切る。心臓の鼓動をも合わせるつもりで動き、一人一人にフォーカスを合わせ、撮る、撮る、撮る。
舞台上で繰り広げられるそれぞれの運命は、舞台の上でのみの運命。現実とは無縁であり、終幕とともに消え去ってしまう。しかしそれでは余りに忍びない。だから舞台を撮る者が要るのだと、僕は勝手に思っている。
余談だが、これを書くにあたって飯名さんのエッセイを読み千葉の勝浦に慶人さんが幼少の頃に住んでいたこと。そこでの蛇にまつわる想い出について知った。僕も伯父と伯母が勝浦に居て、子どもの頃はよく畑の茂みに潜む大きな蛇を見つけたり、畦道で小さな蛇を捕まえたりしたものだった。だからか今でも勝浦というと蛇、というイメージがある。撮影当日はお守り代わりに持っている蛇の指輪をつけていた。そんなことから勝手に縁を感じてみたり不思議に思ったりするのだが、恐らくは人の想いと謂うものは、いつの時代も自分勝手なものなのだろう。偶然の一致を感じ、それを縁や運だと捉える。そして物事は大体偶然に依るところが多いのだ。岡田とお玉の出逢いも、小鳥が蛇に襲われたことも、石が雁に当たって死んでしまったことも、慶人さんが立つこの舞台が一雄さんの命日の上演になったことも、そして僕がその写真を撮ったことも、世の全ては偶然なのだ。そしてそれら偶然は面白いように引き寄せ合う。ただの偶然で終わらせてしまっては忍びないとでも謂うかのように。

[筆者略歴]
GO
http://go-photograph.com/
1970年札幌生まれ。写真家。1995年から広告写真家の専属アシスタントを勤め、後に写真家・浅井愼平氏に師事。2000年、故大野一雄氏を自宅稽古場で撮影したことを契機に舞台写真も撮り始める。現在はフリーランスとして幅広く活動中。