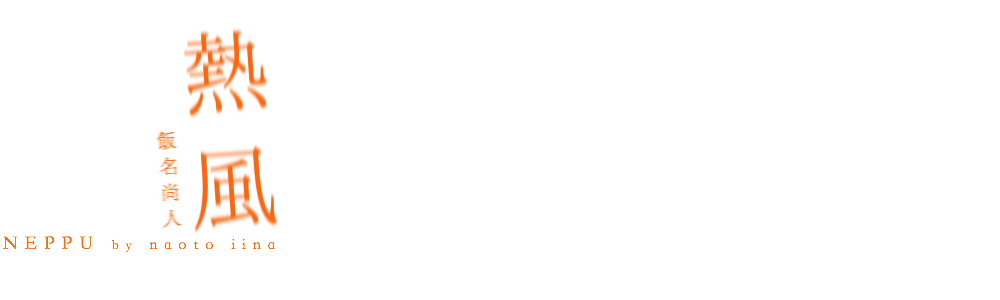大谷 燠、映画「熱風」について語る
ー どちらかが消えて、どちらかが残る
聞き手/水野立子
映画の中で、沖縄の古い映画館が舞台になっていたでしょ。あれ、いいねぇ。古ぼけたピンク映画のポスターが貼ってありましたね。僕は大阪のど真ん中で育っているので、首里とは全然違うのでしょうが、何かある種、似ている空気を感じたんです。子どもの頃、近所の繁華街道頓堀を入って行くと、ストリップ小屋があったんです。そのストリップ劇場の前を通ると、看板が気になって気になってしょうがなくて(笑)。それを観てはいけないし、観たいし、というあの頃の感覚を思い出しました。

「熱風」の映画は、滅茶苦茶いいなと思ったんです。すごい流動感があって。映画の始まりに双眼鏡を覗く少女(村上瑠音)が出てくるのが、客観性を示唆しているのかなと思って。この映画には、視点のおもしろさがありましたね。登場人物二人、ガイドと監督を映しているカメラの視点と、ガイドが観ているだろうと思う視点、その他に3つか4つの視点がありますね、その映像がすごく巧みで、映像としてのリアリティを感じるところがとても心地良い映画だと思いました。反対にストーリーそのものは、現実と非現実が交差していますね。その事と映像のマッチングの巧みさが、映像として見やすかった。

川口隆夫さんの存在には、圧倒されましたね。以前ダンスボックスで「トリック」という舞台作品をやった時の川口さんより、とても研ぎ澄まされた感じがしてビックリしたんです。すごくよかったですね、ラリッている感じと、おネエ言葉が、あのガイドの不思議さをすごく表現していた。
ガイドの話で、「ある日熱風が吹くと、溶ける人と溶けない人がいる。溶けない人のほうが悪いんじゃないの?」というところがありましたよね。それはいろんな読み方ができるなあ、と思った。もちろん原発のこともイメージしてしまったんですが、僕は昔行った広島のことをイメージしたんですね。それは、溶けた人の影だけが残っている石。原爆を投下された時、人が瞬間的に消えてしまって、その人の影だけが映された石が展示されていたんです。そういうのを思い出して、人の存在の在り方の危うさというか、そういうものが、とてもシュールレアリスティックにある、というような感じがした。芸術というものを僕らが体験している時のリアルな現実と、超現実、実はその両方の中で人間は生きているのだ、ということを定義しているようで面白かったですね。そして最後、予定どおり溶けるというね(笑)。喋らない煙草ばかり吸っている俳優(笛田宇一郎)がよかった。

映画の前の<第2幕 写真>の章にも出てくる場所―モスクワ、キューバ、サラエボから沖縄に繋がってくる、そういう“場”として象徴的な場所。戦いの場所だったり、異なる価値観がぶつかってきた場所、境界のある場所として提示されているなと思ったんですが、こういう場所として密度の濃い場所がある。そこには熱い風が必ず吹いて、どちらかが消えて、どちらかが残る、それが今、世界の色々なところで実は起こっているんだ、ということを暗示するような作品だと思いました。
(了)
大谷 燠(おおたに いく)
NPO法人DANCE BOX Executive Director
1996年に大阪でDANCE BOXを立ち上げ、多数のコンテンポラリーダンスの公演、ワークショップをプロデュース。2009年4月、神戸・新長田に拠点を移し、劇場≪ArtTheater dB 神戸≫をオープン。新進の振付家・ダンサー ・制作者を育成する「国内ダンス留学@神戸」や、「KOBE-Asia Contemporary Dance Festival」など国際交流事業のほか、アートによるまちづくり事業も多数行う。
神戸大学、近畿大学非常勤講師。2010年度国際交流基金地球市民賞を受賞。